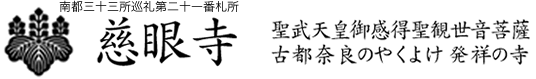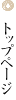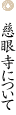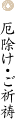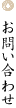『悪党 重源』 レヴュー
なかなか本を読む時間もないですが、そんな中、久しぶりに興奮して一日で読み切ってしまいました。
『悪党 重源』
あくまで歴史小説であって、資料的な裏付けとか、そういうことにはちょっと目をつぶって、重源の「上人」じゃない部分をとにかく魅力的に描いた本作。大仏再建への苦労を色々ちまちま描くのではなく、稲光の閃きの中に、そのすさまじい重源の人生の場面場面が浮かび上がるような、疾走感のある作品でした。
信心深く徳の高い高僧ではなく、やり手の土建屋さんの成り上がり一代記です。めちゃくちゃカッコイイ。とにかく出てくる人がみんな一筋縄ではない。ほぼ全員手がデカくてゴツゴツした無口なオッサン。血なまぐさい剣客モノみたいな雰囲気です。好き勝手やっててとても気持ちいいですね。
キーワードは「自力」。「南無阿弥陀仏」を名乗る重源の一代記なのに、隅から隅まで手作業、腕っぷし、度胸一本。利用できるものは何でも利用するマキャベリズム。
「悪党」というのは、この場合、「既存のルールから外れた者」という意味です。タクティクス・オウガでいうとカオスルートですね。自分の力だけで自由に道を切り開いていく者という意味です。「在家」とは、「この世の理の中にいる者」のこと。出家するとは、すべての繋がりを絶ってしまった者のこと。この世の規則やルールから離れたぶん、自分で自分の食い扶持を得なければならない。ただ本堂でお経をあげていればいいお坊さんとは全く違います。
「悪党」が俗世の理から離れているのは、象徴的な意味合いだけではありません。その生活圏、経済システム、はては歩く道路や海路すらも、普通の「みち」から離れた「けものみち」に通じています。山師とかマタギであるとか香具師など、定住せずに各地を回る人々がそうであったように、本書に出てくる弔い法師、犬山師、無宿僧などはみな、日本中の稼げる場所にネットワークを張り巡らし、神出鬼没に現れては、互いを出し抜く実力主義の世界の住人です。彼らの行う「勧進」は、何も経を唱えて寄付を募ることだけではない。と、いうより、そんなものは単なる「舞台装置」でしかない。いかに人を集め、人を手配し、それによってお金を集めるか。これが「勧進」の内実です。
兵庫小野の浄土寺の堂内には確かに極楽浄土と見まがう美しい景色が現われますが、あの巨大な阿弥陀如来もまた、浄土寺に寄進を行うことに経済的意味を見いだした人々が、その経済活動がそこにあったからこそ、あの場に立っているわけです。そしてその一帯の荘園を管理し、ヒト・モノ・カネのネットワークを構築したやり手の経営者、重源の存在なくしてあの極楽浄土はない。西日を背にして浮かび上がる阿弥陀如来の威容。それは阿弥陀如来を中心とした経済循環のプロデューサーである重源の、計算づくの最高の演出なのだと感じさせます。
後ろ盾も相続する家督もない。そうした世間の「家」の理からは出てしまっている。だから自分の腕しかない。師匠の技術は目で盗み、一回見たら二度と忘れない。生き残るためにはその師匠も喰らうリアリズム。これがこの作品で描かれている重源の「悪党」ぶりです。
願って願ってお経をあげていれば大仏が立つわけではない。
木はどこで伐採するのか。どうやって運ぶのか。金・銀・銅・錫、瓦に大甕、縄も大量に要る。人夫をかき集め、彼らを食べさせ、給金を払う。そのすべてにカネが要る。そして同時に、それらを動かす推進力として人の心を動かさねばならない。
そのいわば「演出」のために、快慶は仏像をつくりました。今でいえば特撮を使ったCMです。公式キャラクターです。慶派仏師もまた、信仰心だけで働いたわけではない。各地でパトロンをおさえ、幕府だけ、貴族だけに偏らぬよう、どちらが覇権をとっても慶派が生き残れるよう、東国では運慶が、西国では快慶が中心となってチーム制で仏像制作をしました。快慶と重源の繋がりは相当に深いですが、人間的、信仰的繋がりだけで二人が繋がっていたとは限りません。お互いの利害関係も一致したからこそ、二人の協働はありえたのかもしれません。そういう意味では、仏像だってリアルな存在です。天平仏、白鳳仏、平安仏、鎌倉仏。ただの流行だけではない。国家事業だから乾漆像は作りえた。チーム作業だから寄木造ができた。寄木造だから玉眼の細工ができた。信仰の対象にも「経済」も「技法」も歴然としてある。平たく言えば、誰かが思いっきり汗をかかなければ生まれないものなんですね。
その「汗」の部分のリアリズムを体現するような「怪僧」といっていいのが重源であり、その姿を徹底的にハードな味付けで仕上げてくれたのがこの、『悪党重源』でした。
身分秩序が固定される前の中世のダイナミズムに徹底的にフォーカスした作品ともいえるでしょう。いやぁ面白かった。コレはオススメですね。
『君の名は』もいいですけど、全然爽やかではないこういう作品も、たまにはどうぞ。