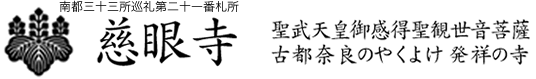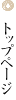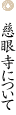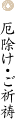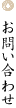どろろー欠損と無常と―
2018年からアニメが当たり年に入りまくっている気がします。2019年もその傾向は続き、見なきゃと思いつつ、見られていない作品がまだまだあります。
現在放映中の「どろろ」もかなりいいと思います。
原作はもちろん読んでいたのですが、百鬼丸の悲劇的な運命に比べ、本人の性格があまりに闊達で、ちょっと違和感があったのも確か。ストーリー漫画でありながら、基本的にはぶつ切りの短編の連続のようでもあり、結局長編として一つの物語としては成立できずに終わったような感覚がありました。手塚治虫は3巻くらいの長編か、BJのような一話読み切り形式の数珠つなぎのほうが向いている気がします。そのへん現代版手塚ともいうべき、浦沢直樹と通じるところがありますね。
まだ5話までしか見ていない段階ですが、フェティシズムさえ感じるこだわりと、映像美。さらにはものすごい仏教的テーマも孕んだ良作だと思います。あと、手塚治虫に対するリスペクトもきっちり感じます。手塚治虫ってフェティシズムの作家ですからね。
とにかく作品全体に「欠損」がいたるところにキーワードとしてちりばめられています。
百鬼丸自体が、「欠損」の象徴のようなキャラクターであり、そのへんがちょっと現代映像化するのはちょっと難しいかな?と思ったのですが、見事に映像化してくれています。
最近は義手、義足を敢えて前面に押し出して「アート」として表現する動きも出てきています。差別だとか色々難しいところではあるのですが、これはユニークフェイスの問題などにも通じるところがあり、「ギョッとしてほしくないから見慣れてくれ」という主張は大いにありますし、そうした部分に「美しさ」を感じて写真集が出ていたりします。「切断ヴィーナス」なんていうショッキングな写真集が普通に買えます。そこにフェティシズムを感じることまで大っぴらにすべきかどうかはまた議論の分かれる難しい問題かと思いますが、「美」というのはつまるところフェティシズムである、というのも一面の真理ではあり。これは「見せる側」の自意識にも左右されると思うのですが、我々「ふつう」だと思われている人間にしても、たとえスタイルがよかろうが顔がきれいだろうが、見せたいかどうかはその人次第。「見せる側」として一まとまりにはできませんからね。
いずれにせよ、「目を背けるべきか。じろじろ見るべきか。」の二者択一ではない「これが俺の普通なんだ」という本来当たり前の主張がかえって出にくくなる事態だけは避けてほしいなと思います。拒絶でも礼讃でもないものが。
で、「どろろ」。とにかく「欠損」がでてくる。これでもかこれでもかというほど。残酷なシーンも多いです。これをただのグロだとか、この手のフェチの人だとか言うのは簡単なのですが、どうもそういう感じもしない。
むしろ百鬼丸の「つくりもの」の部分の表現が秀逸です。最初は、攻殻機動隊のときに感じたドールフェティシズムめいたものかと思っていたのですが、違うような気もします。
現状百鬼丸はまだ眼を取り戻していないのですが、この「つくりもの」の眼のなんという表現力か。ホンモノの眼をもつキャラの何倍も雄弁に感情を語るのです。さらにいえば、第一話の顔すらまだ得ていない、「面」をかぶっている状態の彼から、むきだしの「生」への執着を感じる。この「欠損と獲得」のアンヴィバレントな構造は、実は原作でも存在していました。
百鬼丸は魔物を倒すごとに、奪われた身体や感覚を一つずつ取り戻していくのですが、彼が本来あったものを取り戻すごとに、彼の戦闘能力は落ちていくという皮肉な結果がもたらされます。第六感で会話し、相手を認知し、痛みも感じず、「つくりもの」の手足で化け物を倒していくスーパーヒーローが、徐々にごく普通の人間に戻って行く。
失うことは得ることであり、得ることは失うことである。
これこそが「どろろ」のテーマであり、それは仏教的無常観そのものであると言えます。
財産や栄光や愛する人などの「幸せ」は、得た瞬間から、失われることが運命づけられます。逆説的に言えば、何かを得ないと失うことはできない。何かを失うということは、何かを得ていたということ。何かを得るということは、それがいつか必ず失われるということ。喜びは悲しみのはじまり。悲しみは喜びのはじまり。
+と-は必ず帳尻が合い、やがて無に帰す。
百鬼丸は初めて得た聴覚に混乱し、動けなくなり、はじめて得た声で激痛の咆哮を響かせる。
我々がこの世に生まれ落ちた瞬間、最初に出す声は、苦痛の叫びであるのと同様です。
このテーマが至る所にちりばめられる。
醍醐が得た領地の富や力は、すべて百鬼丸を生贄にして得たもの。百鬼丸が身体を取り戻していくごとに、それらはすべて失われていく。そして、そんな人一人の間の+と-の外側では、「いくさ」という、より大きな+と-を繰り返しながら、大いなる無へと向かう巨大なうねりが無慈悲にすべてを飲み込んでいく。
これらはすべて、原作のなかにしっかり存在したテーマでもある。そこがすごい。
私は。手塚治虫が何もかもお見通しで、深遠な哲学の下に作品を描いていた、なんて思わないんですよね。あの人は確かに天才ですが、ただの漫画家であるといえばそれまでなんです。ただのケモノフェチのエロい線を描くおっさんで、ほとんどの天才がそうであるように、虚栄心が強くて、他人の成功に我慢ならない、つまり普通の人間なんです。
ただ、「漫画を描くのが異常に上手い」というこの一点の才能を、彼が突き詰めた結果、日本人の死生観や無常観がすべて手塚治虫という一人の天才を通して作品として結実してきたという事実に感動すらおぼえます。まるでヘーゲル。まんまヘーゲル。ベレー帽をかぶった世界精神ですね。
百万のごたくより、一枚の絵は遥かに雄弁です。
手足の義肢をほっぽり出して、抜身の刀を振り乱しながら、ケモノのように戦う姿。手足が生えてくる痛みに震えながら、歯を食いしばってただひたすら歩き続ける姿。
そこに私は「生きること」を見る。
その先に積み重ねる幸せも苦しみも、やがて崩れさるべきものであり、それゆえその先には「無」しか存在しないことを知りながら、それでもただひたすら前を向き、「つくりもの」の足で歩を進め、血まみれで剣を振るい続ける姿は、やはりそれでも―。
これは「欠損」の物語。
失われたものを嘆き、失われることを恐れ、それらすべてがまるごと失われる我々の物語。